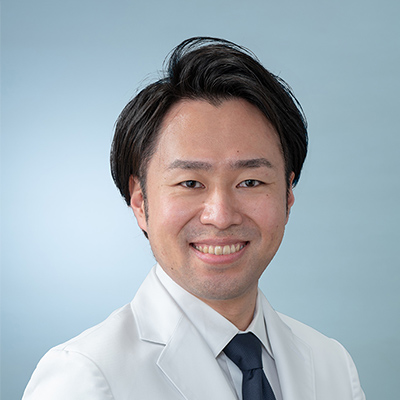VOICE OF A WORKING DOCTOR
はたらく医師の声
-留学経験-
-留学経験-
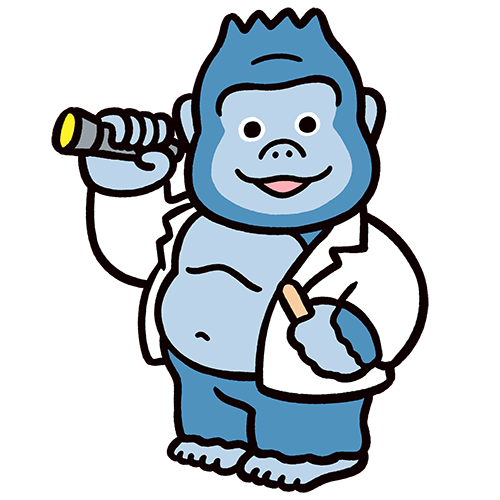



VOICE
新しい挑戦に対する憧れと、
未知の学びへの期待
新しい挑戦に対する憧れと、
未知の学びへの期待
未知の学びへの期待
未知の学びへの期待
留学先:北海道大学病院
横田崇之先生
国内留学についての背景と動機
私は以前から「留学」という形で新しい環境で学びたいと考えておりました。その中で、日下教授と北海道大学小児科の真部教授のご厚意により、急遽国内留学の提案をいただきましたが、迷わず即決いたしました。血液腫瘍について集中的に学べる環境への期待が大きかった一方で、単身赴任による家族との離別や給与面での不安があったことも事実です。しかし、新しい挑戦に対する憧れと、未知の学びへの期待がその不安を上回りました。
留学中の学びと経験
北海道大学での3か月間は、主に病棟業務を中心に行いました。特に印象に残ったのは、それまで経験したことのない入院症例に多く出会えたことです。懸命な治療にもかかわらず、予後が厳しい患者様に対するケアを通じて、「緩和ケア」の重要性についても幅広く学ぶことができました。
また、北海道大学では各分野ごとに専門チームが組織されており、さらに他分野の先生方とのカンファレンスがほぼ毎日のように開催されていました。活発かつ熱のこもった議論が印象的で、診療の質を高めるチーム医療の真髄を肌で感じることができました。これらの経験は、今後の臨床現場での診療に大いに役立つものと確信しています。
留学を通じて得たものと今後への影響
全く異なる環境での研修は、多くの学びと挑戦に満ちています。学んだ知識や技術だけでなく、新たに得られる人とのつながりは、医師としての人生を豊かにする貴重な財産となります。一歩踏み出すことに躊躇することもあるかもしれませんが、その先にある成長や充実感は計り知れません。
短期間でも新しい環境で得た経験は、日々の診療や人生観に大きな影響を与えてくれるはずです。ぜひ、挑戦することを恐れず留学を検討してみてください!
これから留学を考えている学生・研修医へのメッセージ

思い出の北海道の風景
全く異なる環境での研修は、多くの学びと挑戦に満ちています。学んだ知識や技術だけでなく、新たに得られる人とのつながりは、医師としての人生を豊かにする貴重な財産となります。一歩踏み出すことに躊躇することもあるかもしれませんが、その先にある成長や充実感は計り知れません。
短期間でも新しい環境で得た経験は、日々の診療や人生観に大きな影響を与えてくれるはずです。ぜひ、挑戦することを恐れず留学を検討してみてください!

VOICE
国内でトップレベルの小児アレルギー診療を経験。
ナショナルセンターで働かれる先生方のお考えは
非常に刺激になりました
国内でトップレベルの小児アレルギー診療を経験。
ナショナルセンターで働かれる先生方のお考えは非常に刺激になりました
ナショナルセンターで働かれる先生方のお考えは 非常に刺激になりました
ナショナルセンターで働かれる先生方のお考えは非常に刺激になりました
留学先:国立成育医療研究センター
荻田博也先生
『国立成育医療研究センター アレルギーセンターでの国内留学を終えて』
2019年4月から2021年3月の2年間、国立成育医療研究センターのアレルギーセンターで専門修練医として小児アレルギー疾患について多くのことを経験させていただきました。この2年間、非常に充実した日々を過ごすことができましたので、後輩の先生方への「国内留学のすゝめ」となることを願いながら、またひとつでも参考になることがあればと思い留学体験記を記させていただきます。
国立成育医療研究センターは厚生労働省所管の国立研究開発法人であるナショナルセンター(国立高度専門医療研究センター)であり、小児科領域が約30の専門分野に細分化され日々診療を行っています。私が所属していたアレルギーセンターは、アレルギー疾患における国の中心拠点病院として、診断が困難な症例や標準的治療では病状が安定しない重症・難治性アレルギー疾患の患者さんに対し、関係する複数の診療科(総合アレルギー科、皮膚アレルギー科、消化管アレルギー科、鼻アレルギー科など)が連携することで、専門診療を提供することを目的に2018年6月に設置されました。また世界アレルギー機構(World Allergy Organization)からCenter of Excellenceに指定され、国内はもとより世界中の専門施設の指導的役割を担う施設でもあります(成育医療研究センターホームページより)。

私が国内留学を希望したきっかけは、国内でもトップレベルの小児アレルギー診療に携わる先生方のもとで経験し、指導を受けたいと考えたことでした。
医師になってから5年間、大学病院や総合病院等において上級医から小児科一般診療の指導を受けながら勤務しておりましたが、医師6年目になり医長として初めて上級医のいない環境で勤務することとなりました。もともと小児科医を目指したきっかけが小児アレルギー診療に携わることでしたので、日々の診療でも細々とアレルギー診療を行っておりました。一方で、自身の研鑽と経験だけでは大幅なスキルアップには限界があることも痛感していました。この経験から、いつか世界で活躍している先生方のもとで学び、診療技術を磨いて香川のアレルギー診療の役に立つことが私の目標となっておりました。
そんな中、どの施設で学びたいかを考え一番に頭に浮かんだのが、私が所属させていただいた国立成育医療研究センターでした。センター長である大矢幸弘先生は国内外問わず小児アレルギー診療並びに研究でご活躍されており、過去に私が参加した学術大会でお見かけした講演数は数多く、小児アレルギー診療に携わる医師で知らない者はいないのではないかと思います。そうして本施設での勤務を希望し、本施設の専門修練医に応募致しました。大変ありがたいことに本施設のアレルギーセンターで採用いただくこととなり、医師8年目からの国内留学が決定致しました。
それでは、この2年間の国内留学で経験したことを思い出しながら感想とともに述べさせていただきます。
まず1つ目に臨床経験についてです。重症アトピー性皮膚炎や好酸球性消化管疾患等の地方で一般小児科医をしていると多く経験することのない小児アレルギー疾患を経験することができました。毎週のカンファレンス以外にも、各専門の先生方には普段から気軽に治療方針等を相談でき、建設的な意見をいただくことができ非常に学びやすい環境でした。また食物アレルギーに関しても、経口食物負荷試験だけで連日8-10名程実施しており、規模の違いを感じました。
2つ目に、国内外の学会発表についてです。医師として日々の診療で経験し考えたことを報告することは非常に重要なことです。私自身過去の報告や文献のおかげで多くのことを学んできました。留学期間の2年間で、日本アレルギー学会や日本小児アレルギー学会、The European Academy for Allergy and Clinical Immunology、World Allergy Organization等で演題発表させていただきました。昨今の社会情勢のため現地開催が少なかったのは残念でしたが、上級医の先生方には発表準備の段階から沢山アドバイスをいただくことができ、考え方のプロセス等非常に勉強になりました。
3つ目は臨床研究についてです。まず驚いたのはアレルギーセンター内では多数の研究が同時並行で実施されている事でした。それもエビデンスレベルの高い前向きコホート研究やランダム化比較試験が当たり前のように実施されておりました。ありがたいことに、私もその中でいくつかの研究に携わらせていただきました。これまで臨床研究の経験はなく全てが初めての事ばかりでしたが、研究計画と倫理審査、参加者のリクルート、研究実施、その成果の発表にはいつも指導医の先生がアドバイスを下さり、何とかやり遂げることができました。
学会発表や臨床研究の内容は論文化することを基本としており、ナショナルセンターとしての役割を常に考えておられる先生方のお考えは非常に刺激になりました。いつもお忙しい中で論文執筆の指導もしてくださったおかげで、アレルギーセンター在籍中に論文投稿できたことも良い経験になりました。
上述のように、当時の私は地方で一般小児科医としての勤務経験しかなく、アレルギーセンターの先生方とは面識もなかったため専門修練医への応募は正直不安もありました。しかしアレルギーセンターの先生方はお人柄も尊敬できる方ばかりで、指導体制も充実しており、2年間働くことができ本当に満足しておりますし、大矢センター長や指導医の先生方へは感謝の気持ちしかありません。また同世代の小児アレルギー専門医を志す先生方と知り合えたことも財産です。また香川に戻ってからも臨書研究員としてアレルギーセンターに在籍させていただき、引き続き論文執筆等の指導をいただけるとあたたかいお言葉もいただくことができました。
もしこれから国内留学を考えている先生がおられましたら、是非勇気を出して飛び込んでみて下さい。新しい施設で自身の目指す専門領域で活躍されている先生や、同じ志を持つ同世代の先生との新しい出会いはきっと刺激となり、将来自分が医師としてどうなりたいかがみえてくると思います。
最後に、大矢センター長をはじめ、アレルギーセンターの皆様、2年間本当にお世話になりました。国立成育医療研究センター アレルギーセンターで学んだことを、香川の小児アレルギー診療に還元できるよう精進してまいります。また国内留学を許可して下さった日下教授、ならびに専門施設での勤務を後押しして下さった元職場の指導医の先生にも感謝申し上げます。

VOICE
医療もグローバル社会となりつつあり、
様々な国の方とのコミュニケーションは必須。
そのコンプレックスが解消されたことは収穫でした
医療もグローバル社会となりつつあり、様々な国の方とのコミュニケーションは必須。そのコンプレックスが解消されたことは収穫でした
様々な国の方とのコミュニケーションは必須。
そのコンプレックスが解消されたことは収穫でした
留学先:The University of Washington Medicine
岩城拓磨先生
2年間、米国シアトルのThe University of Washington Medicineに留学されていた岩城拓磨先生のインタビューです。
- どんな研究をされていたのですか?
-
私は小児科全般を診療していますが、その中でも小児腎臓病に力を入れてやっています。

(研究ラボの建物)
2013年4月から2015年3月までアメリカ合衆国ワシントン州シアトルのUW (University of Washington) Medicineで研究留学の機会をいただき腎臓病の研究をしてきました。シアトルはアメリカの北西部に位置し、山と湖と緑に囲まれたとても美しいエメラルドシティありでイチローの活躍でも一躍脚光を浴びました。またMicrosoft、Amazonを初めとしたIT系の企業がひしめき最先端の技術を求め世界中からたくさんの研究者、技術者がやってくる北西部最大の都市です。またスターバックス発祥の地でもあり香川のうどん屋並みにスターバックスがあります。シアトルでは2つの研究所で別々の研究をしました。 1つ目の研究所では肝腎症候群における急性腎障害に対してRelaxin投与が有効かどうかという研究をしました。内容です。Relaxinは妊娠期に発現が増える蛋白で出産に備えて骨盤周囲の靭帯を緩める(文字通りrelaxさせる)働きがありますが腎血管拡張作用もあるとみられている蛋白です。Relaxinの受容体であるRXFP1の腎臓での発現を主に研究しました。
2つ目の研究所では敗血症による急性腎傷害に対しperoxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα)という中性脂肪のβ酸化を促す転写因子が病態を改善させるかどうかを研究しました。
いずれの研究所でも免疫染色、PCR、Western blottingにより組織や細胞レベルでの蛋白の発現を調べることにより分子生物学的な病態解明を目指しました。 - 研究の大切さで感じたことはどんなことですか?
-
仮説を立て研究によって病態が解明されれば治療法のオプションは増えますし今までに治療法がなかった難治性疾患が治療できるようになるかもしれません。現代の高度な医療は先人達の地道な研究によって成り立っていることを忘れてはいけないと思います。

(Mount Rainier)
- 海外留学をしてよかったことはどんなことですか?
-
医療もグローバル社会となり医学発展のために成果を世界中に発信しなければなりません。そんな中で英語を使うことや外国人の方とのコミュニケーションは必須になってきています。そのコンプレックスが解消されたことが一番の収穫でした。また異国の方との交流は本当に楽しいものでしたしその中で日本人の良さを再認識させられました。もちろん医学研究大国のアメリカでたくさんの研究ノウハウを取得することができたことも大きな財産です。

(右から2番目が筆者)
- これから留学したいと思っている方へメッセージをお願いします
-
小児科は様々な領域の疾患を扱っていますし、小児は成長、発達をするので成人とは全く違った視点で研究すべきことがたくさんあります。私達も医療の質を上げるために日々成長してく必要があると思っています。大学病院は色んな医師や研究者と交流があり留学のチャンスが多いと思います。ただ初めから特定の分野の興味を持つ必要はなく仕事をしていく上でやりたいことがみつかることもあります。実際に私もそうでした。特に力を入れてやりたいことができればそれを応援する体制が私達の医局ではできています。今回も医局員みなさんの応援で留学を実現することができました。
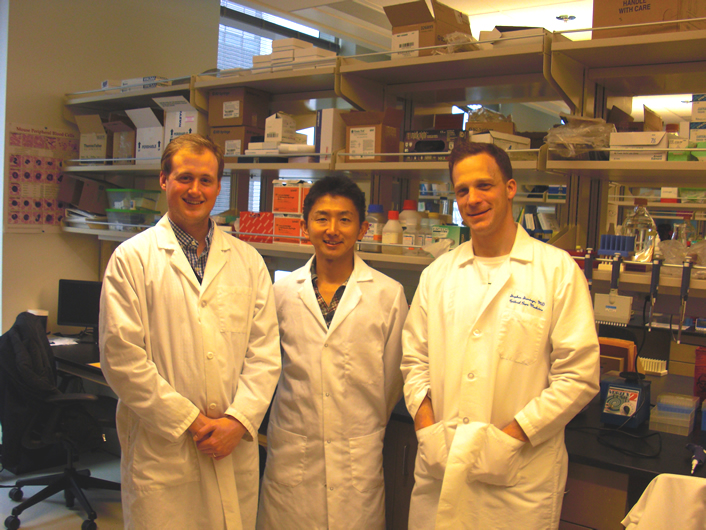
(研究室にて 中央が筆者)

VOICE
世界的にトップクラスの研究所で
「自分の考えを相手にはどのように伝えるか?」
ということの重要性を痛感し、常に考えるようになりました
世界的にトップクラスの研究所で「自分の考えを相手にはどのように伝えるか?」ということの重要性を痛感し、常に考えるようになりました
「自分の考えを相手にはどのように伝えるか?」
ということの重要性を痛感し、常に考えるようになりました
留学先:The Ritchie Centre,Hudson Institute and Medical Research
中村信嗣先生
オーストラリアのThe Ritchie Centre, Hudson Institute and Medical Researchに留学していた中村信嗣先生へのインタビューです。
- 留学しようと思ったきっかけはなんですか?
-
留学する3年前に、アメリカ・コロラド州デンバーであったアジア小児科学会とアメリカ小児科学会の合同学会で発表する機会がありました。そこで、論文や教科書でよくみかけていた海外の先生たちに自分の研究内容を高く評価して頂きました。それがきっかけで研究に専念するようになり、研究にもっと集中できる海外でしっかりと研究をしたい!と思うようになりました。
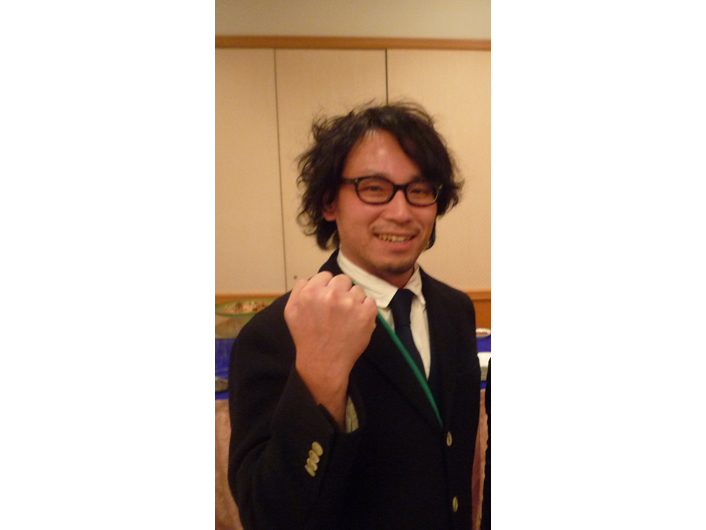
- 海外留学の経験から何を学びましたか?
- 胎児生理学研究において、世界的でもトップクラスである私の研究所(The Ritchie Centre, Hudson Institute and Medical Research)では、20代から70代までの科学者たちが年齢を問わず議論し合い、切磋琢磨し合っています。このような環境の中では、自分の考えを執拗なまでに伝えなければ、研究は進みませんし、何も始まりません。このため、「自分の考えを相手にはどのように伝えるか?」ということの重要性を痛感し、常に考えるようになりました。特に言語面でのハンディがありましたので、できるだけシンプルに説明するようになりました。また、このために、日本にいたときよりも多くの論文を読み、講演会・研究会にも積極的に参加しました(週1回は研究所内でセミナーが開催され、ほとんどの論文は無料で読むことができました)。そこで得たものは、自分の研究分野に関する深い知見だけでなく、日本でいる時には興味がなかった分野のことなども多くあり、自分が大きく成長できたと感じました。

(2010.4 撮影 台湾の学会で)
- 海外生活は不安ではなかったですか?
- 生活するうえで言語面の問題が、本当に苦労しました。しかし、「習うより慣れろ」で、少しずつ家族もオーストラリアの生活に慣れていきました。子供たちは、現地校に通ったのですが、のびのびとしたオーストラリアの教育システムが肌に合ったようで、すぐに学校が大好きになりました。特にお子さんがおられる方とって、教育環境が整っており、子供に対して寛容であるオーストラリアは、子育てにはもってこいだと思います。

ビクトリア州南部フィリップ島にて
- 休みの日などはどのように過ごしておられましたか?
-
オーストラリアは自然が大変豊かであり、野生のカンガルーがたくさん生息する国立公園に家族でピクニックに行ったり、長期休暇には、家族でキャンプにでかけ、オーストラリアの大自然を思いっきり満喫しました。夏は、庭で子供たちはプールで遊び、大人はBBQをしながら、のんびり過ごす、ということも多かったです。特に、年末年始にキャンプにでかけた際に、南半球の満点の星空を眺めながら、家族・友人らと過ごした年越しは、一生の思い出です。

カンガルーをいなしているところ
- 若手医師の方々へのメッセージ
- よく、「わざわざ海外に行かなくても・・・」とか、「日本の医療は世界でもトップクラスなのだから・・・」と言って、海外留学は無駄だと考える人がいます。しかし、幕末に欧米に渡った若き志士たちは、その後、大きな革新を日本にもたらしました。英語を全く話せなかった私たちの先祖たちは、勇気をもってその一歩を踏み出したのです。私たちに足りないのは、英語力でしょうか?決してそうではありません。世界の大海原へ勇気をもって一歩を踏み出したとき、新しい革新が始まると思います。