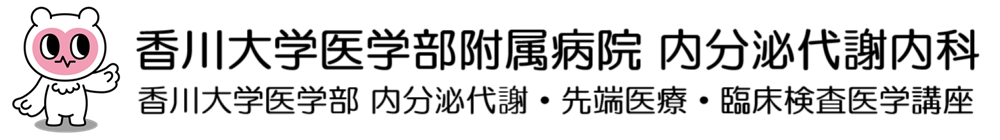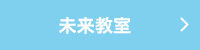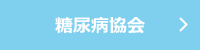第20回合同地方会(日本臨床検査医学会)
第20回合同地方会(日本臨床検査医学会)
会長:大塚文男先生(岡山大学総合内科学)
会期:令和6年2月17−18日
特別講演『HDL代謝と疾患』
香川大学医学部内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学
村尾孝児、井町仁美、福長健作、小林俊博、佐伯岳信、吉村崇史
抄録
High-density lipoprotein (HDL)は一般的には善玉コレステロールとして認識されている。臨床検査ではHDLコレステロールの量が測定され、総コレステロール、LDL-C, TGなどとともに評価されるが、疾患の直接的な評価とはなっていない。一方、LDL-Cは悪玉コレステロールとして、その受容体の遺伝子異常は家族性高コレステロール血症と診断され臨床的な意義が明らかにされている。HDL代謝には3つの重要なステップがあり、それぞれ ApoA1, ABCA1, SR-BIがその主要分子となる。HDL代謝と疾患との関連を考える上では、それぞれの分子の遺伝子異常と臨床的な表現形を考える必要がある。ABCA1の遺伝子異常であるタンジール病は、血中HDL-C・ApoA1濃度が著しい低値を示す常染色体劣性遺伝疾患であり、HDL-C欠損症のほかオレンジ色の咽頭扁桃腫大、角膜混濁、末梢神経障害が特徴である。加えて高度な中性脂肪血症、脂肪肝、糖尿病の合併が報告されている。SR-BIの遺伝子異常に関しては、これまでに1家系のみが報告され、動脈硬化性疾患の罹患に関しては指摘されていない。SR-BIの遺伝子異常では、高HDL血症、血小板の形態異常及び副腎皮質機能の低下が報告されている。一方、ヒトSR-BIに対する自己抗体が検出されることが高安病で報告されており、血管内皮細胞での機能も注目されている。2型糖尿病に伴う脂質異常症は高中性脂肪血症および低HDL血症である。さらには2型糖尿病の原因として膵β細胞における糖毒性のみならず、脂肪毒性が注目されており、脂肪毒性によるインスリン分泌の低下が指摘されている。これら2型糖尿病の病態にもHDL代謝が関与することが報告され、脂質代謝と糖代謝の接点が指摘されている。今回は我々の研究室の結果も含めて、最近のHDL代謝研究について概説する。