第15回【令和5年(2023年)1月29日(日)】
テーマ「子どもの病気やケガに対する救急対応や電話相談」
第15回香川県小児保健協会研究会は、2023年1月29日(日)にweb会場をメインに香川県立保健医療大学を聴講会場として開催しました。
県下から専門職の方、一般の方、学生さん等69名の参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「子どもの病気やケガを保護者が安心して見守るために」をテーマに大阪府小児救急電話相談事務所長 福井聖子先生にお話しいただきました。
また、「香川県#8000における現状と課題」をテーマに香川県健康福祉部医務国保課課長補佐 藪根正浩様に講演していただきました。
香川県の子ども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
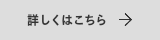
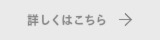
第14回【令和4年(2022年)2月6日(日)】
テーマ「子どもの成長と発達をめぐる環境の現状と課題」
第14回香川県小児保健協会研究会は、2022年2月6日(日)にweb会場をメインに香川県立保健医療大学を聴講会場として開催しました
県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計78名の参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「成人移行支援(トランジション)における子どものヘルスリテラシー獲得と健康への支援」をテーマに国立成育医療研究センター 窪田 満先生にお話しいただきました。シンポジウムでは、日頃小児保健にご尽力いただいている先生方から、子どもの発育をめぐる生活環境の課題について、ご提言いただき、参加者で共有できました。
香川県の子どもたちの福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
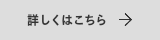
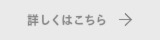
第13回【令和3年(2021年)2月7日(日)】
テーマ「医療的ケアを必要とする子どもの育ちを支える地域づくり」
第13回香川県小児保健協会研究会は、2021年2月7日(日)に、web開催をメインに香川県立保健医療大学を聴講会場として開催しました。
県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計90名の参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「医療的ケア児の受け入れに関する基本的な考え方と支援体制の構築」をテーマに松井剛太先生にお話しいただきました。シンポジウムでは、日頃小児保健にご尽力いただいている先生方から、医療的ケアを必要とする子どもの育ちを支える地域づくりについてご提言いただき、参加者で共有できました。
香川県の子ども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第12回【令和2年(2020年)2月2日(日)】
テーマ「子どもの発達障害」
第12回香川県小児保健研究会は、2020年2月2日(日)に、香川県立図書館内 文書館2階で開催しました。県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計122名のご参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「自閉スペクトラム障害における幼児期の睡眠障害の特徴について」をテーマに小西行彦先生に、「乳幼児期における自閉スペクトラム症の睡眠について」をテーマに坂井 聡先生にお話しいただきました。
香川県の子ども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第11回【令和元年(2019年)2月3日(日)】
テーマ「子どもとメディア」
第11回香川県小児保健研究会は、2019年2月3日(日)に、香川県立図書館内 文書館2階で開催しました。県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計88名のご参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「小児科医からの提言 ~子どもとメディア」をテーマに日下 隆先生にお話しいただきました。シンポジウムでは、日頃小児保健にご尽力いただいている先生方から、子どもとメディアについてご提言いただき、参加者間で共有できました。
香川県の子ども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第10回【平成30年 2月4日(日)】
テーマ「小児の生活習慣病の現状と予防」
第10回香川県小児保健研究会は、平成30年2月4日(日)に、香川県立図書館内 文書館2階で開催しました。県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計106名のご参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「地域に根ざした小児医療の構築」をテーマに伊藤 進先生にお話しいただきました。シンポジウムでは、日頃小児保健にご尽力いただいている先生方から、小児の生活習慣病の現状と予防についてご提言いただき、参加者間で共有できました。
香川県の子ども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第9回【平成29年 1月29日(日)】
テーマ「食育・かがわのこどもたちの食事を考える」
第9回香川県小児保健協会研究会は、平成29年1月29日(日)に、開催場所を香川県立図書館内 文書館2階で開催しました。県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計144名のご参加をいただき、活発な意見交換ができました。「子育て世代包括支援 ~妊娠・出産・育児の切れ目のない支援~」高松保健センターの方にお話しいただきました。シンポジウムでも、香川県栄養士会、助産師会、歯科医師会、三豊・観音寺市医師会、三豊市子育て支援課から食育について活動について各先生方からご提言いただき、香川県の食育への取り組み状況の実態や課題について参加者間で共有できました。
香川県のこども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第8回【平成28年 1月24日(日)】
テーマ「香川県の小児虐待への取り組み」
第8回香川県小児保健協会研究会は、平成28年1月24日(日)に、香川県立保健医療大学で開催されました。県下から専門職の方、一般の方、学生さん等計102名のご参加をいただき、活発な意見交換ができました。特別講演は「虐待対応を含めた小児の救急-多施設・多職種との連携の必要性について-」のテーマで岩瀬孝志先生にお話しいただきました。シンポジウムでも、日頃小児虐待予防についてご活躍されている先生方からご提言いただき、香川県の小児虐待への取り組み状況の実態や課題について参加者間で共有できました。
香川県のこども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第7回【平成27年 1月25日(日)】
テーマ「香川県の地域小児医療の取り組み」
第7回香川県小児保健協会研究会は、平成27年1月25日(日)に、香川県立保健医療大学で開催されました。テーマは「香川県の地域医療の取り組み」で、計110名のご参加をいただきました。特別講演は「ワクチンで予防できる病気(VPD)」をテーマに永井崇雄先生にご講演いただき、シンポジウムでは、日頃小児保健にご尽力いただいている先生方から、こどもの健康問題についての取り組みについての発表があり、会場の皆様と意見交換ができました。
研究会が香川県のこども達の福祉に貢献するという目的のもと、人と人をつなぐネットワーク作りにつながることを目指していきたいと思います。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第6回【平成25年12月8日(日)】
テーマ「香川県を日本一こどもの育てやすい県にするには」
第6回香川県小児保健協会研究会は、平成25年12月8日(日)に、香川県立保健医療大学で開催されました。テーマは「香川県を日本一こどもの育てやすい県にするには」で、計84名のご参加をいただきました。伊藤会長の講演はじめ、子どもの健康や発達支援に日頃からご尽力されている方々をお迎えしてのシンポジウムや一般口演で活発な意見交換ができました。アンケートからは、「これだけ多職種が集まる会はありません」、「連携の大切さを感じます」等のご意見や、一方で「時間が足りない」とのご指摘もありました。
この研究会が香川県のこども達の為の、よい情報交換の場となり、人と人をつなぐネットワーク作りにつながればと思いました。まずは継続することです。さらなる皆様のご支援をお願いします。
![]()
![]()
第1回【平成20年11月30日(日)】
記念すべき第1回開催
香川県での保健医療活動において、香川県小児保健協会は2年前より市民公開講座として「Baby-Kids Health Care-幸せなママのための家庭医学と看護」、「メディアと育児環境-子どもの身体と心が危ない-」を行ってきましたが、これまで十分な役割を果たしていませんでした。香川小児保健協会は、小児保健医療に関心のある医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、保健師、栄養士、教員および保育士、県や市の行政の皆様などからなります。最近の子どもを取り巻く環境において、虐待、非行、フリターやニートおよび生活習慣の増加を減少させ、子どもが健全に育成するために力を合わせて、子どもの成育環境においても全国一良い県にしようではありませんか(会長挨拶より、一部抜粋).
![]()
![]()
